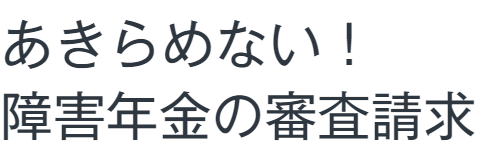関節リウマチの初診日の医証(医師の証明)がない、第3号被保険者期間
2 前記認定された事実に基づき、本件の問題点を検討し、判断する。
(1) 初診日に関する証明資料は、これが障害基礎年金の受給権発生の基準となる日と定められている趣旨からいって、直接これに関与した医師又は医療機関が作成したもの、又はこれに準ずるような証明力の高いものでなければならないと解される。
(2) 請求人は、当該傷病の初診日を平成7年12月26日と主張するが、当該主張は、資料2の同人自身の申立内容と矛盾するものであり、また、平成5年12月24日当時のE整形外科の診療録の記載内容からして、それが平成5年12月以前にあることは疑いがない。資料1においては、当該傷病の初診日は請求人の主張するように平成7年12月26日であり、これを診療録で確認したとあるが、前記1の(2)にあるように、後に訂正されている。
(3) 請求人が平成3年に当該傷病でG病院を受診したことを同病院の診療録等で直接確認することはできない。しかし、同人が当該傷病で障害基礎年金の裁定請求をする10年以上前の、同人が同年金の支給要件について強い関心を持っているとは認めがたい平成5年12月当時の同人の申立に基づき、E整形外科の診療録に記載されているので、平成3年頃G病院整形外科受診は信じるに足るものである。またこの点は、資料2によっても裏付けられ、請求人自身が平成3年7月にG病院を受診したと申し立てている。なお資料7には、請求人が平成7年12月26日の「8年前からリウマチ治療中」とあるが、これは必ずしも8年前の昭和62年頃にリウマチで医師の診療を受けていたことを意味しない。
これらの点からすると、保険者が当該傷病の初診日を平成3年7月31日と認定したことは妥当であると認めることができる。
(4) 当該傷病の初診日が平成3年7月31日であるから、保険料納付要件を満たすためには、その前日において、請求人の平成3年5月までの被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間と保険料免除期間であるか、平成2年6月から同3年5月までの1年間がすべて保険料納付済期間又は保険料免除期間であることが必要になる。
(5) 請求人には、第3号被保険者期間があるが、その取扱いは以下のようになっている。
すなわち、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号(以下「平成11年改正法」という。)による改正前の法の定めるところによれば、法第7条第1項第3号により、同項第2号にいう被保険者(以下「第2号被保険者」という)の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者であるものを除く)のうち20歳以上60歳未満のものは、第3号被保険者とされているところ、同被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項を厚生省令の定めるところにより、市町村長に届け出なければならない(法第 12条第1項及び第105条第1項)とされていた。
これを承けた国民年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第7号による改正前のもの)第6条の2は、第1号被保険者が第3号被保険者となった場合、当該事実があった日から30日以内に、必要書類を添え、必要事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない旨規定しており、この届出が遅れた場合、当該届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間は、当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除き、保険料納付済期間に算入しない(法附則第7条の3)こととされている。
(6) 請求人は、平成8年11月14日に、国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号、以下「平6改正法」という。)第10条第1項の規定に基づき、同人の保険料納付済期間に算入されない第3号被保険者期間について都道府県知事に届け出たが、当該期間が前記(5)の法附則第7条の3の規定にかかわらず保険料納付済期間に算入されるのは、平6改正法附則第10条第3項の規定により、届出が行われた日以後である。
(7) そうすると、平成8年11月14日の届出によって保険料納付済期間とされた前記1の(2)の昭和62年度から平成4年度までの期間(72月)は、当該傷病の初診日の前日(平成3年7月30日)においては未納期間とされるので、認定事実から、請求人の平成3年5月までの被保険者期間237月中保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間は106月となり、237月の3分の2に欠け、また、平成2年6月から同3年5月までの1年間はすべて保険料納付済期間とされない第3号被保険者期間であり、第3の1の[2]の保険料納付要件を満たさない。
(8) なお再審査請求代理人は、公開審理期日において、請求人は前記(5)の届出がない場合でも第3号被保険者としては認められ、実際には保険料納付義務を負うわけではないので、不注意で届出が遅れた場合には、前記(6)のような数次の特例届出制度を活用することによって、老齢基礎年金の受給に当たっては実質的な不利益が生じないようになっているが、障害基礎年金の場合にはそのような手当がなされていないのは、単なる不注意のペナルティとして著しく均衡を欠くものであり、問題であると陳述した。その主張には、首肯できる点があるとしても、立法政策論であり、当審査会の審査対象とするところではない。
(9) そうすると、請求人の障害の状態が国年令別表に定める程度に該当するかどうかを論ずるまでもなく、請求人は当該傷病による障害に係る障害基礎年金の支給を請求できる者に該当しないというべきである。従って、これを支給しないとした原処分は妥当であって、取り消すことはできない。